どうもです!
パーソナルトレーニングを22年間継続していると、お客様の体で良い悪い状態がいろいろ見えてきます。
これら見てきたものを蓄積していくとお客様への指導する判断材料や、目標到達時間が早くなります。トレーナーとしての洞察力や技術力が経験によって大きくレベルアップにつながっているということですね。
見えなかったものが見えるようになる、「継続は力なり」と言いますがまさに賜物です!
そこで、もう一つパーソナルトレーニングを継続して見えてきたものが、タイトルにもありますが高齢者の前のめり(前傾)姿勢です。特に歩行時の前のめりは加速して転びやすく危険です。
今回は高齢者に共通する歩行時の前のめり(前傾)について考えていきたいと思います。
※後傾の人もいますが今回は前のめりを中心に説明していきます。
身近に多い、高齢者の前のめり(前傾)姿勢は危険です。
この ”前のめり(前傾)姿勢” は、おじいちゃんおばあちゃん、ご両親やお知り合いの人など皆さんの身近にいらっしゃるのではないですか?
まず知ってもらいたいのは
“人は、前のめりになりやすい構造をしている”

これは膝と股関節の屈曲する可動域がもともと広いのが原因なのですが、本来は決して悪いことではありません。
みなさんが普段しゃがむ(屈伸)動作や椅子に座る動作がありますが、それは必ず膝と股関節が屈曲しているから、スムーズな座位が出来るのです。正面を向いて日常生活を送るには欠かせない動作なのはたしかですね。
ただし
筋肉を伸び縮みさせない状態が長く続いていると筋肉は硬くなり体を起こせなくなったりと機能低下につながります。
ここはあまり難しく考えなくて良いと思いますが、人は誰しもが前のめり(前傾)になる恐れがるということは覚えておいた方が良いです。
高齢者が前のめり(前傾)姿勢になっていて歩行しているところをみると、はたから見ていてもなんだか、危なっかしいのがわかると思います。
なぜ危ないのか解説すると
体に対して、頭が前に垂れ下がっていて頭の重さで歩行している状態です。自分の足でコントロールして歩いているわけではないので、つま先が上がらず擦るような歩行になっています。
まさに、つまずき転倒しやすい歩き方といえるでしょう。
ここでスムーズな歩行ができるよう杖を使ったり、歩行器を使ったりと快適な日常動作が送れるように歩行の補助として使用しますが、姿勢のとり方や考え方は基本的に一緒です。杖の目的を理解し取り入れてもらえれば安心しながら、より長く歩くことが出来るようになります。
高齢者の前のめり(前傾)の改善は周りの人の補助が大事!
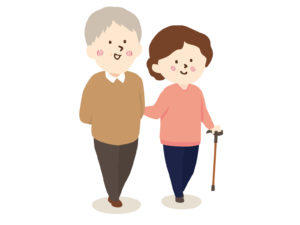
今や高齢化が進み、前のめり(前傾)で歩きにくくなっている高齢者が多くなっています。しかし諦めるのはまだ早い改善する余地は十分にあります。
それは身近な人が助けてあげることです。
といっても専門家のような細かな指導をする必要はありません、身近にいてその人のことを理解しているからこそ、できることがあるということです。
一つ間違っちゃいけないのが、歩くのを支えてあげたり、車椅子に乗せたりという、相手の負荷をとってあげるようなバリアフリー的な意味ではなく、その人が普段やらない動作や行動を促すための、どちらかと言うと運動習慣を身につけるようなことを意味しています。
必要な負荷を与えるということです!
どのようにするのかの前に
これだけは覚えておこう
前のめり(前傾)姿勢は、背面の筋肉を伸び縮みさせていない事の代償として筋肉が凝り固まっていること
が原因です。
これを踏まえてどうすれば良いのか、身近な人ならなんとなくわかる、その人の性格や行動パターン、癖や趣味趣向など、身近な人ほど明確で確率が上がります。
やり方は簡単
まず悪い姿勢になる動作行動を見つけてあげましょう。
例えば
机に向かって本を読む、パソコンしたりなどの作業が多い、寝ている時の枕が高い、介護用ベッドの背中上げが高い、立っている時や歩いている時に頭が前のめり(前傾)で猫背になっている、など
これらに共通するのは、お尻の筋肉が硬くなっている状態なので、お尻の筋肉を使う股関節周りを動かすような動作行動にもっていけると良いということです。
改善方法として、ストレッチや体操もありますが一番分かりやすいのが
【歩行】をすること
歩行は両腕を左右に振りながら胴体は捻られ、両足に体重が乗りバランスをとるために体を起こし左右に足を動かし前に進む、というお尻の筋肉を使い股関節を動かす全身運動になるからです!
結局は歩行することが一番なのですが、
ポイントはお尻を意識させるように歩いてもらえるとより前のめり(前傾)が改善されます。
お尻の筋肉を意識した歩き方の解説はこちらの記事です。
ここで良く相談を受けるのが
「身内の言うことは聞いてくれない」
これは相手がどうしても ”やらされている感” があるとやらないものです。
無理やりやらせるのではなく上手に促すのです。相手に習慣化せるためにも継続できそうな方法をみつけてあげる、それを一番理解している人は身近な人になるということですね。
いくつかコツがあります!
歩かせるためには、散歩や買い物や食事に出かける、あとは新聞を取りに行いく、ポストを見にいく、ゴミを出しにいく、など生活の中で習慣になるような作業を作ってあげることで歩行する筋肉の衰えを予防し改善させることにつながります。
高齢者でも前のめり(前傾)を改善して正しい歩行に戻す力がある

体を維持しようと元に戻す力が誰しもがあります。
ゆる太が、実際にお客様のパーソナルトレーニングをするときは、まずいろいろお話させていただきます。
例えば、学生時代の話・過去の運動歴・趣味趣向・好き嫌い、などやご家族から、どういうお人柄なのか、などご本人以外の人からイメージなんかの情報をもとに、仮説➩検証➩分析をしながらトレーニングに反映させていきます。
ただ正しいトレーニングを与えるだけではなく、その人に”今”必要なトレーニング提供することが大事ということです。
これにより、運動を継続することにつながり筋肉は少しずつ機能しはじめ、前のめり(前傾)が改善されてくるのです。
ゆる太は、22年間実施してきて実際に改善してきた人達をみてきました。
例えばこれが身近な人なら、どんな性格でどのような行動をとるかなど、だいたい把握していることだと思いますので、そこから逆算して運動を与えてあげればいつの間にか習慣化し、自ら行動するようになってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか、高齢者の前のめり(前傾)姿勢は長年の癖からいつの間にか曲がってしまう、それを戻すには正しい日々の習慣が必要です。
しかし無理やりやらせてもやりません、まずは運動を継続させることを重視して考えていけると良いですね。
ポイント
- 誰しもが前のめりになる可能性がある
- 歩く時はお尻周りの筋肉を使う意識をもつ
- 無理やりやらせるのではなく誘導する
- 体は正しい機能に戻そうとしてくれる
これらを頭に入れてアプローチしてあげましょう。
もし、ご家族やお知り合いの人に前のめりを改善したい人がいたらご連絡ください。
無料レッスンでアドバイスさせていただきます。
ただいま、無料体験レッスンを実施中です。
お気軽にお問合せ下さい。









